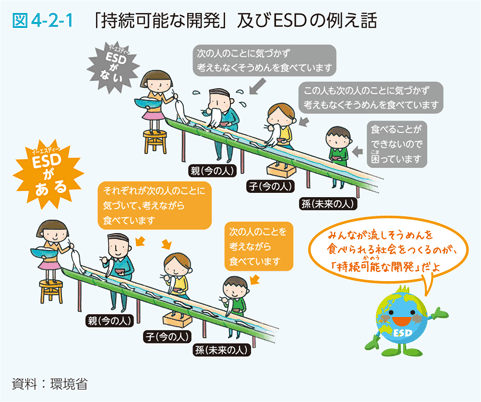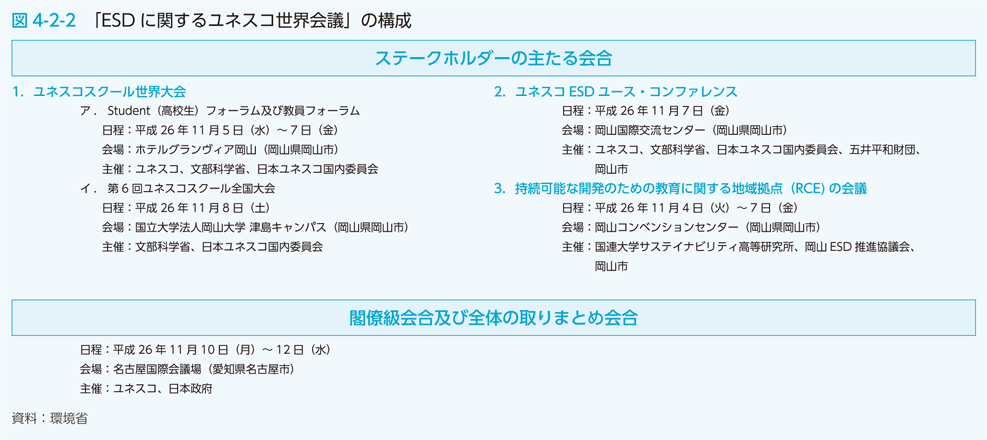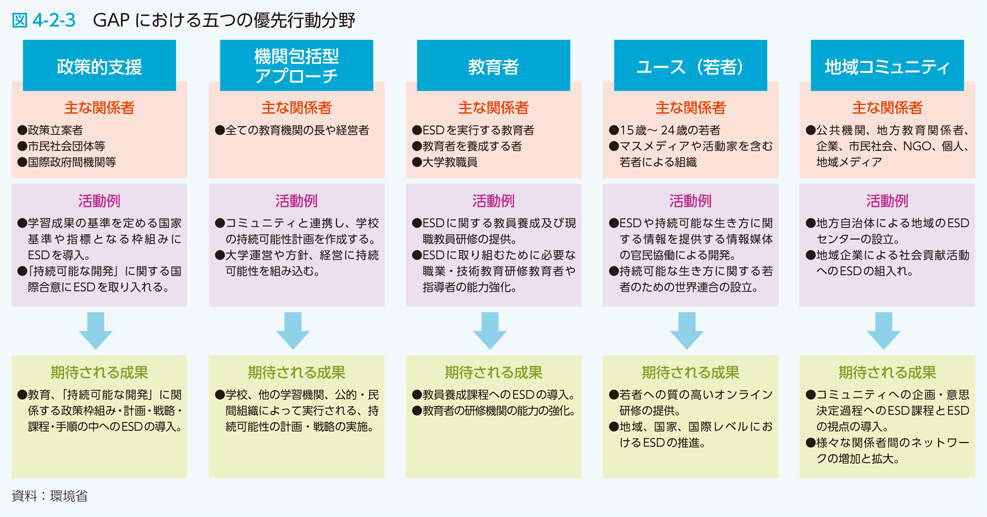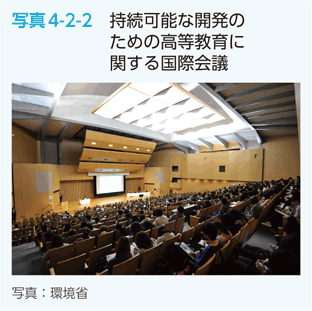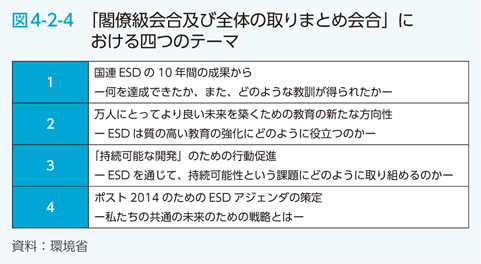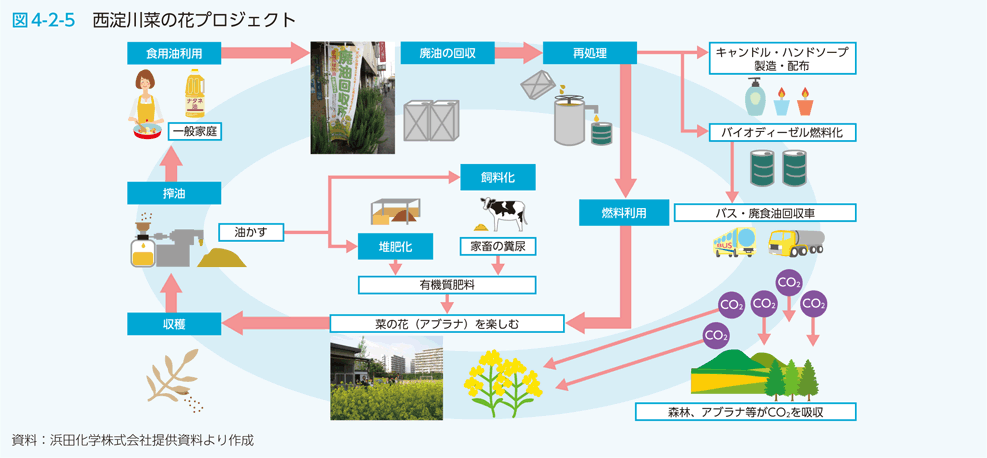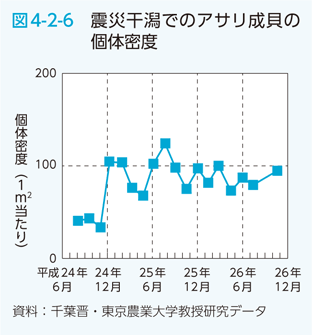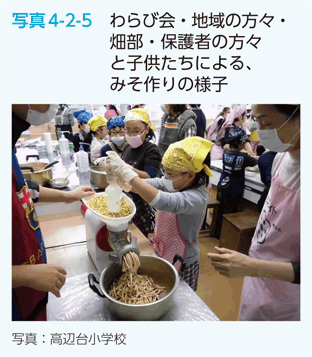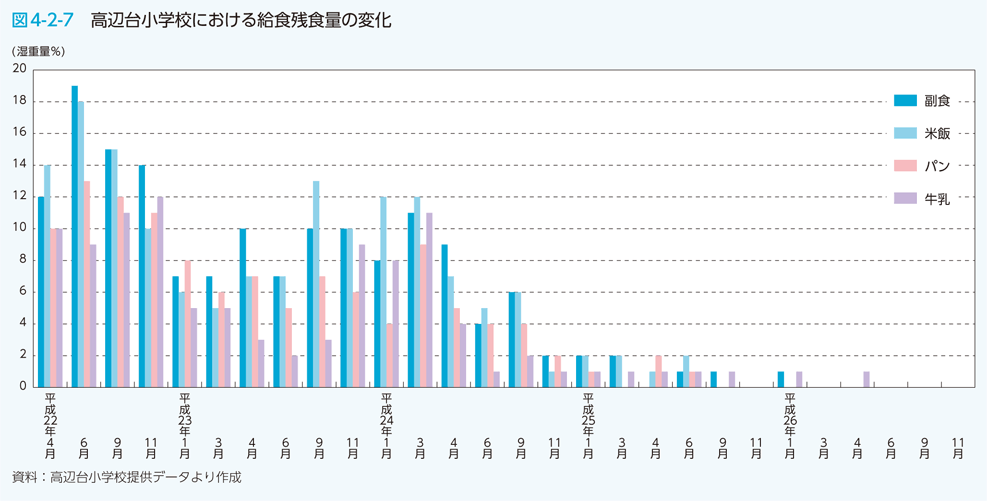第2節 「持続可能な開発のための教育」の必要性
今日、環境保全は、人類の生存基盤に関わる極めて重要な課題となっています。大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、環境保全と健全な物質循環を阻害します。また、温室効果ガスの排出による地球温暖化問題、天然資源の枯渇の懸念、大規模な資源採取による自然破壊等、様々な環境問題にも密接に関係しています。このため、我が国は、従来の大量生産・大量消費型の経済社会から大きく転換し、自然界から取り出す資源と自然界に排出する廃棄物の質と量を自然環境が許容できる範囲内に抑え、持続可能な活動が行われる社会の構築を進めています。
一方で、世界に目を向けると、BRICS(ブリックス)(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)といった新興国を始め、経済成長と人口増加が顕著な国が数多く見受けられ、持続可能な社会の構築はますます重要となっています。
このような中で、気候変動、資源の枯渇や生物多様性の損失といった環境問題を解決するためには、政府、事業者、非営利団体(以下「NPO」という。)、個人等の多様な主体が適切な役割を果たす必要がありますが、これらを構成するのは、つまるところ「人」であり、国民一人ひとりが「持続可能な開発」を意識して、行動を変えていく必要があります。ここでは、そうした意識・行動を変える上でのキーワードとなる「持続可能な開発のための教育(ESD)」について紹介します。
1 「持続可能な開発のための教育(ESD)」とは
(1)「持続可能な開発」及びESDが生まれた背景
我が国では、戦後の高度経済成長期に公害問題が顕著化し、住民に大きな被害が発生しました。特に、水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病及び四日市ぜんそくの「四大公害病」は、社会問題として大きく取り上げられました。一方で、欧米等の国々も酸性雨や農薬等の化学物質を始めとする環境問題に悩まされていました。米国の生物学者であるレイチェル・カーソンが1962年(昭和37年)に出版した「沈黙の春」は、殺虫剤等に含まれていたDDT等の化学物質の危険性を訴え、世界の環境保護活動の端緒となりました。このように、公害のような環境問題は、人類の永続的な繁栄を脅かすものとして考えられるようになりました。
そのような背景を踏まえ、「持続可能性」という考え方が醸成されていきました。1984年(昭和59年)には、我が国の提案により「環境と開発に関する世界委員会」(以下「ブルントラント委員会」という。)が国連に設置されました。ブルントラント委員会が1987年(昭和62年)に公表した報告書「我ら共有の未来(Our Common Future)」では、「持続可能な開発(Sustainable Development)」について、「将来の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満足させるような開発」と定義されました。
1992年(平成4年)には、ブラジルのリオデジャネイロで「国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)」が開催され、「持続可能な開発」の指針である国際的な行動計画「アジェンダ21」が採択されました。アジェンダ21の第36章「教育、意識啓発及び訓練の推進」では、「持続可能な開発」のために意識啓発を推進することが重要である旨が明記されました。
我が国は、「持続可能な開発」の達成のためには人材育成が重要であることを鑑み、2002年(平成14年)に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)」で、2005年(平成17年)~2014年(平成26年)を「国連持続可能な開発のための教育の10年(UN Decade of Education for Sustainable Development、以下「国連ESDの10年」という。)」とすることを提唱しました。
この提案に基づき、第57回国連総会において、「国連ESDの10年」が採択され、国連教育科学文化機関(UNESCO、以下「ユネスコ」という。)がその主導機関となりました。これ以後、「持続可能な開発のための教育(ESD)」の取組が、我が国を含む各国・各地域の様々な主体により取り組まれることとなりました。
(2)持続可能な開発のための教育(ESD)について
「持続可能な開発」は、私たち一人ひとりが日常生活や経済活動の場で意識し、行動しなければ実現しません。そのためには、私たちが世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変えることが必要です。そのきっかけを作り、問題意識を醸成して、行動につなげるための教育がESDです。
図4-2-1では、「持続可能な開発」を流しそうめんの仕組みに例えて説明しています。「持続可能な開発」は、「将来世代のことも考えて、そうめん(資源)を自分の世代で消費し尽くさないようにしよう」ということであり、そのような問題に気付くために、ESDは役立ちます。
ESDの取組分野としてなじみ深いのは、地球温暖化対策や資源リサイクル、自然環境保全等の環境に関する課題について、その重要性を知り、理解した上で、アイドリングストップやごみの分別、自然保護ボランティア等、自分の身近なところで活動するという「環境教育」です。他にも、災害のことを知り、それに備えて防災訓練等の備えを行う「防災教育」や、海外の文化を知り、海外の人々と交流して自分たちと異なる文化を尊重しあう「国際理解教育」等もESDに含まれます。
また、ESDは、
[1]フォーマル教育(学校教育)、
[2]ノンフォーマル教育(学校外教育。正規の学校教育制度の枠外で組織的に行われる教育活動)、
[3]インフォーマル教育(日常の経験、家庭、職場、遊び、マスメディア等の生涯にわたる組織的ではない教育プロセス)を包含しており、その対象も老若男女を問いません。
2005年(平成17年)、ユネスコは「国連ESDの10年」についての国際実施計画を策定し、世界の国々や国連・国際機関等がESDを推進していくための方針を示しました。これを踏まえ、我が国も平成18年に「我が国における『国連持続可能な開発のための教育の10年』実施計画」を策定(平成23年に改訂)し、政府としてESDを推進しています。
2 持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議
(1)会議の概要
「国連ESDの10年」の最終年である平成26年11月に「持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議(以下「ESD世界会議」という。)」が「国連ESDの10年」の提案国である我が国で開催されました。
会議は図4-2-2に示す構成となっており、11月4日~8日に岡山県岡山市で開催された、国連機関、研究者、学校関係者等による「ステークホルダーの主たる会合(以下「ステークホルダー会合」という。)」での議論の結果が、11月10日~12日に愛知県名古屋市で開催された「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」での議論に反映されました。
「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」では、「国連ESDの10年」を振り返るとともに、「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(以下「GAP(ギャップ)」という。)」を今後推進していくための議論が行われました。GAPとは、「国連ESDの10年」より先、すなわち2015年(平成27年)以降のESDの推進方策であり、五つの優先行動分野が示されています(図4-2-3)。
以下では、主に環境省が関わった会議について紹介します。
ア 持続可能な開発のための教育に関する地域拠点(RCE)の会議
「持続可能な開発のための教育に関する地域拠点(RCE)の会議(グローバルRCE会議)」は、平成18年から毎年開催されています。今回、「ステークホルダー会合」を構成する会議の一つとして、第9回会議が、11月4日~7日に岡山コンベンションセンターにおいて開催されました(写真4-2-1)。「ESDに関する地域の拠点(Regional Centres of Expertise on ESD、以下「RCE」という。)」は、地域レベルでのESD活動を推進するために国連大学が認定しており、各RCEは大学、地方自治体、市民団体、NPO等から構成されています。
第9回会議には、世界129のRCEのうち68のRCE(47の国・地域)から272名(うち海外から164名、国内108名)の参加者が集い、我が国からも中部、仙台広域圏、兵庫-神戸、北九州、岡山及び横浜の六つのRCE全てが参加しました。
この会議では、ESDに関する能力開発、政策の推進、モニタリングと評価、気候変動、持続可能な消費と生産、生物多様性、高等教育、若者の参加等のテーマ別課題における議論が行われ、これまでの活動の成果及び今後の課題が共有されました。さらに、今後RCEがどのように発展し、ESDの地域拠点としての機能を高めていくか及びESDを通して「持続可能な開発」の実現にどのように貢献できるかについて、GAPを踏まえ議論しました。その議論を基に、「国連ESDの10年」以降も「持続可能な開発」に関する様々な国際的枠組み等への支援を行うことにより、RCEが持続可能な社会づくりに寄与することを宣言する「2014年以降のRCEとESDに関する岡山宣言」を採択しました。
本宣言は、愛知県名古屋市で開催された「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」で共有され、同会合での議論に寄与しました。
イ 持続可能な開発のための高等教育に関する国際会議
「持続可能な開発のための高等教育に関する国際会議」は、ESD世界会議の関連イベントとして11月9日に名古屋大学において開催され、66か国から約750名の高等教育関係者が参加しました(写真4-2-2)。会議の冒頭には北村環境副大臣が開会挨拶を行い、ESDの取組における高等教育機関の役割の重要性に言及するとともに、ESDの主要な関係者である“ユース(若者)”の参加について謝辞を述べました。
この会議では「国連ESDの10年」を振り返り、高等教育機関による様々な取組がESDの促進に果たした成果と、持続可能な社会を創り出すために不可欠な高等教育機関の役割及び責任が共有されました。この議論の結果を基に、世界各地の様々な指導者に対し、「持続可能な開発」の実現に向けて、革新的な取組を主流化することのできる高等教育の役割を支持するよう呼び掛ける「持続可能な開発のための高等教育に関する名古屋宣言」が採択されました。
この宣言についても、愛知県名古屋市で開催された「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」で共有され、同会合での議論に寄与しました。
ウ 閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合
この会合は、日本政府とユネスコの主催で、11月10日~12日に名古屋国際会議場において開催され、153の国・地域から閣僚級76名を含む約1,000名が参加しました。この会合では、「ステークホルダー会合」での成果を踏まえた議論が行われました。図4-2-4に示す四つの具体的なテーマに基づき、「閣僚級会合」のほか、NGO等の様々なESDの関係者も参加する四つの全体会合、34のワークショップ及び25の公式サイドイベントが開催されました。
11月12日に開催した第3回全体会合では、「教育は持続可能な開発のゲームチェンジャーか?」というテーマで、環境省から高橋環境大臣政務官がパネリストの一人として登壇し、ESDを実施する人材の育成や教材開発、関係者の連携といった点を今後の重要な課題としていく必要があることを発信しました(写真4-2-3)。
また、環境省は、公式サイドイベント「日本におけるESDの成果と今後」を、様々なESD関係者を交えて開催しました。我が国でこれまでに実施されてきたESDの取組と、「国連ESDの10年」において環境省が取り組んできた国内外でのESD事業について、その知見を参加者と共有するとともに、環境省における2015年(平成27年)以降のESDの推進方策を公表しました。
会合の最終日である12日には、「ステークホルダー会合」及び「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」の両成果を踏まえ、GAPを後押しし、2015年(平成27年)以降に策定される各国の政策にESDを採り入れることを呼び掛ける総括文書である「あいち・なごや宣言」が採択されました。あわせて、GAPを2015年(平成27年)から開始していくことを公式に宣言しました。
(2)ESD世界会議の成果を踏まえた今後の取組
ESD世界会議開催後の2014年(平成26年)12月には、第69回国連総会でGAPが決議され、2015年(平成27年)から推進されるESDの取組がより確固たるものとなりました。
また、2012年(平成24年)には、「国連持続可能な開発会議(Rio+20)」が開催されており、その成果文書「我々が望む未来」において、「ESDを促進すること及び国連ESDの10年以降も『持続可能な開発』を教育に統合していくことを決意する」と明記されています。
さらに、『我々が望む未来』において、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals、以下「SDGs」という。)」を策定することが盛り込まれており、2014年(平成26年)に国連でSDGsについて議論された際にも、ESDがSDGsに盛り込まれる方向で検討されました。こうした背景を踏まえ、世界の様々なESDの関係者が、持続可能な社会の実現に向けてESDを推進しています。
現在、我が国においても、ESD世界会議の成果及びGAPを踏まえ、2015年(平成27年)以降のESDの取組を更に加速させています。気候変動枠組条約、生物多様性条約、「持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み」といった条約や枠組みにおいても教育の重要性と役割が示されており、この点がGAPでも明言されています。
そのため、これらの条約及び枠組みを推進する環境省では、GAPを踏まえ、グローバル及びローカルな視点に基づき、「人材の育成」、「教材・プログラムの開発・整備」、「連携・支援体制の整備」を柱に据えて、ESDを更に推進しています。また、環境省、文部科学省、内閣官房、外務省を含む11府省で構成される「持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議」において、「我が国における『国連ESDの10年』実施計画」をGAPを踏まえて再編成し、展開していくことで、持続可能な社会の構築を進めることとしています。
3 持続可能な地域づくりにおいてESDが果たす役割
第1章でも述べたとおり、我が国は人口減少や超高齢化、人口偏在の進行によって、地域の疲弊・荒廃が深刻化しており、持続可能な地域づくりの重要性が高まってきています。
また、第3章でも見てきたとおり、地域の人々はその地域特有の歴史的資源や自然資源、文化・社会資源という地域資源の価値を再認識し、その地域資源を生かしてエコツーリズムや伝統行事等の恩恵を受けながら、魅力的な地域づくりを行うという行動を新たに起こすことにより地域活性化に取り組んでいます。各地域で既に実施されている地域の課題を解決するための活動にESDの視点を取り込むことで、こうした活動を持続可能な地域づくりの取組へと発展させることが可能となります。
こうした背景を基に、環境教育を推進することで国民一人ひとりの環境保全に対する意識や意欲を高め、持続可能な社会づくりにつなげていくために制定されていた、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)が、平成23年に改正されました。本法の基本理念(第3条)には「持続可能な社会の構築のために社会を構成する多様な主体がそれぞれ適切な役割を果たすとともに、対等の立場において相互に協力して行われるものとする」と規定されており、行政、企業、民間団体等の協働取組の重要性がより明確になっています。
特に、持続可能な地域づくりを進めていく上で、その地域を支える地域住民や地域に根ざした民間企業、NPO等が果たす役割は、非常に大きいと考えられます。例えば、環境に配慮した取組を各主体が理解し、連携しながら考えて行動していくことで、その地域は環境にやさしく、そして住みよい地域となります。このような地域が、ESDの実践の場として機能し、ESDの取組が活性化することで、更に持続可能な地域づくりの取組を促進するという「好循環」が生まれることが期待されます。
以下では、そうした個人や民間企業、NPO、学生等の多様な主体が、ESDを通じた持続可能な地域づくりに取り組んでいる事例を紹介します。
(1)西淀川菜の花プロジェクト
大阪府大阪市西淀川区は、阪神工業地帯に位置し、工場群が集積する地域です。また、主要国道と阪神高速道路が通り、かつては光化学スモッグ等の公害問題が深刻化しました。こうした背景を踏まえ、西淀川地区の地域住民らが中心となって、平成18年に「持続可能な交通まちづくり市民会議」を立ち上げ、「西淀川ESD協議会」と連携して、「西淀川菜の花プロジェクト」に取り組んでいます(図4-2-5)。
協議会のメンバーである地元の大阪府立西淀川高校では、ESDの一環としてこのプロジェクトを授業に取り入れており、学生は校内の未利用のスペース等を利用して菜の花(アブラナ)を育てています。ここで収穫したアブラナから作られたナタネ油は地域の方々に提供され、料理に使用された後の廃食油が地域の町内会等で回収されています。
回収された廃食油は、本プロジェクトに協力している浜田化学株式会社のCSR活動の一環として、バイオディーゼル燃料(BDF)や廃食油キャンドル、ハンドソープ等に無償で加工されます。こうして作られたバイオディーゼル燃料は地元で廃食油回収車や市民バス等の燃料として利用されており、廃食油キャンドルは、電気の明かりを使わずに夜を過ごす西淀川の環境イベント「キャンドルナイト in NY(西淀川)」で使用されています。また、地元の中学生がラベルデザインしたハンドソープは、廃食油回収に協力された方々や西淀川地域内の公共施設等に配布されています。
この取組では、廃食油がバイオマス燃料としてバス等の燃料等に活用され、そこで排出されたCO2を新たに植えたアブラナが吸収することで、「カーボン・ニュートラル」な取組となっています。さらに、軽油の使用量を削減することができ、結果的に大気汚染物質の一つである硫黄酸化物の発生を抑えることができます。加えて、廃油を回収することで台所からの排水が汚れないという、環境負荷低減効果もあります。
このプロジェクトでは、高校生、大学生、ガールスカウト、地域の町内会や商店街、廃食油のリサイクルを行う企業等の多様な主体が協力しながらそれぞれの地区単位での取組を進めています。こうした多様な主体が各地区の環境の重要性に気付き、考えて行動することで、ESDを通じた持続可能な地域循環型社会が構築されています。
(2)「森は海の恋人」運動
宮城県気仙沼市を拠点とした「NPO法人森は海の恋人」は、気仙沼の「牡蠣(かき)士(同地方での、優れたカキ養殖家の敬称)」で、現在同NPO法人の理事長を務める畠山重篤さんが開始した「森は海の恋人」運動がきっかけとなって誕生しました。
気仙沼湾の環境は、昭和40~50年代にかけて悪化しました。その結果、ツノフタヒゲムシという赤潮プランクトンで真っ赤になったカキが、「血ガキ」と呼ばれて売れなくなりました。そこで畠山さんは、「森は海の恋人」運動を開始しました。川は、カキの餌となる植物プランクトンが生育する上で不可欠な窒素やフルボ酸鉄といった養分を山から海へ供給しています。このため、「森は海の恋人」運動では、まず、気仙沼湾に注ぎ込む大川の上流部に位置する室根山を「牡蠣(かき)の森」と命名し、広葉樹を植えるなどの里地里山づくり活動を実施して、海の環境の改善を図りました。
「漁民が山に木を植える」というこの活動は、森・里・川・海という広域的なつながりを重視した自然環境保全活動を行った事例として小・中学校の教科書でも取り上げられており、今では子供も含め、多様な主体の参画により取り組まれています。また、京都大学では、森里海連環学の教育プログラムが設けられています。
本法人は現在、森は海の恋人運動の取組を発展させ、気仙沼市舞根(もうね)地区において、震災復興のため「海と生きるまちづくり」を掲げて、科学的な知見を通じたESD活動として環境教育・防災教育を実践しています。
舞根地区は東日本大震災で約15mの津波が押し寄せ、漁業が壊滅的な被害を受けるとともに、約0.8mの地盤沈下が発生して宅地や道路が冠水しました。そこで、被災者でもある本法人の畠山さんが中心となり、漁業による地域の活性化を目指して、研究者や地域のボランティアと協働して現地の環境調査及び環境評価を行いました。その結果、舞根湾の植物プランクトンの季節変動特性が変化して、震災前よりもむしろカキの生育環境が良くなったこと等が明らかになり、カキ養殖等の漁業の再開を後押しすることとなりました。
また、同法人は地域住民、学校やNPO等、延べ約1,000名と協働して環境調査や地形の測量を実施するなど、気仙沼市のまちづくり基本計画の策定にも積極的に携わっています。調査の結果、戦後の干潟の埋立てによって造成された海沿いの農地や宅地等では、震災によりアサリの生息する干潟環境が創出され、アサリの成貝が100個体/m2前後の密度で生息していることが判明しました(図4-2-6)。社団法人全国沿岸漁業振興開発協会が公表している指針では「成貝で200~400個体/m2」がアサリの増殖場を造成する際の目安となっており、これと比べても、アサリの生息数は少なくないことが分かります。この干潟は、現地で「震災干潟」と呼ばれています。
同法人が、震災干潟をアサリ等が生息する浸水低地として保全し、地域活性化のための地域資源として漁業や観光に生かすとともに、津波が来た際の緩衝地帯として活用するということを気仙沼市に提案した結果、その方針がまちづくり基本計画に組み込まれました。こうしたまちづくりに加え、同法人が主体となって、地域住民への防災意識の普及啓発や、震災干潟を使った環境教育といったESD活動も実施しています(写真4-2-4)。
このように、NPO法人を中心に多様な主体が関わり、山と海との関連性・海の持続可能性を重視した山づくりを実施し、また、防災に係る活動や自然環境保全活動を通じて情報を共有し持続可能なまちづくりを行うことも、ESDを通じた持続可能な社会の構築の一環です。
(3)たかべ みそ汁元気いっぱいプロジェクト
大阪府富田林市立高辺台(たかべだい)小学校では、ESDの一環として、PTA、地域住民の方々、富田林市食生活改善推進協議会(通称「わらび会」)、帝塚山学院大学の学生サークル「畑部(はたけぶ)」といった地域の多様な主体約200名との協働の下、「たかべ みそ汁元気いっぱいプロジェクト」として、同小学校の子供たちに畑作りとみそ作りを教えています。同小学校では、その畑で大豆のほか、ダイコン、ネギ、白菜などを育てており、育てた大豆からみそ作りも行っています。また、毎年2月には、子供たちが自分で育てた作物と自分たちで作ったみそでみそ汁を作り、地域の方々と共に味わっています(写真4-2-5)。
本プロジェクトの開始以降、高辺台小学校では給食残食が減少し、富田林市内の16の小学校の中で給食残食の発生量が一番少ない小学校となっています(図4-2-7)。高辺台小学校での残食量の減少という「目に見える」結果は、地元の方々や学生サークル「畑部」の大学生等にもフィードバックされ、本プロジェクトを推進する原動力となっています。
このように、子供たちだけでなく、大人も含む地域の多様な主体が、高辺台小学校が推進する本プロジェクトを通じて「食育を通じた持続可能な社会の構築の重要性」に“気付き”、その結果、地域の食品廃棄物の低減が実現しています。これは、地域で協働して取り組まれているESD活動の好事例です。
転載元: 不法投棄不法占拠対策のブログ


























 ATC(アジア太平洋トレードセンター)は、大阪南港ベイエリアの大型複合商業施設です。
ATC(アジア太平洋トレードセンター)は、大阪南港ベイエリアの大型複合商業施設です。